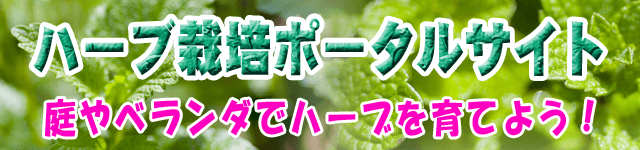
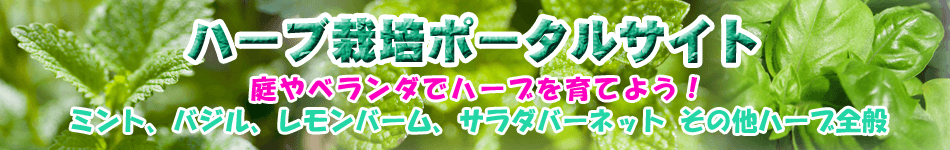
ハーブ栽培TOP > 青じそ(大葉)の育て方 > 乾燥青じそ(大葉)の作り方
■乾燥青じそ(大葉)の作り方
青じそは5月ごろから11月ごろまで長期間葉を収穫できるハーブですが、
寒くなってくると枯れてしまいます。
そこで、枯れる前の葉を有効利用する為に、
大きな葉を収穫したあとに残った葉を乾燥させて、乾燥青じそを作ってみたいと思います。
乾燥させておけば、ひと冬ぐらいは持ちますので、料理にふりかけたり、風味着けに使ったりいろいろと重宝します。
 (2016年10月21日)
(2016年10月21日)
今年もだいぶ葉を収穫させてもらった青じそです。今年は3株育てていて背丈は1m〜1m20cmぐらいになっています。
もうすぐ11月になるので、青じそもあまり成長しなくなりました。
葉が枯れてしまう前に、この残った葉を使って、乾燥青じそを作ってみたいと思います。
 青じその主茎から、葉をつけたままの枝の部分を全てカットします。
写真の左側にあるのは青じその花が終わってタネになる部分です。
これは今回はそのまま料理に使ったりしますので取り除きましたが、
つけたまま葉と一緒に乾燥させてもかまいません。
青じその主茎から、葉をつけたままの枝の部分を全てカットします。
写真の左側にあるのは青じその花が終わってタネになる部分です。
これは今回はそのまま料理に使ったりしますので取り除きましたが、
つけたまま葉と一緒に乾燥させてもかまいません。
 主茎からカットした青じそは、枝に葉がついた状態で水道の流水などでさっと洗います。
洗う時に、ひと枝ごとにごみや虫などがついていないか確認しながら洗って下さい。
また、変色していたり、硬くなっている葉は取り除きます。
主茎からカットした青じそは、枝に葉がついた状態で水道の流水などでさっと洗います。
洗う時に、ひと枝ごとにごみや虫などがついていないか確認しながら洗って下さい。
また、変色していたり、硬くなっている葉は取り除きます。
洗い終わったら、よく水を切り、ひもで束ねてから軒先などの、半日陰で雨がかからないような場所に吊るして数日間乾燥させます。
今回は最後の収穫なので青じそを枝ごと乾燥させましたが、葉のみを大量に収穫した時は、野菜乾燥用のネットなどに入れて乾燥させればOKです。
![]()
 (2016年10月27日)
(2016年10月27日)
青じそを乾燥させてから6日経ちました。
乾燥したかどうかは、天候や乾燥させる場所などにもよりますので、
葉を触ってみて少しの力で葉が粉々に砕ければ乾燥した状態といえますので目安にして下さい。
 乾燥した青じその葉の部分を手でそぎ落とします。
この時に、枝と葉をつないでいる太い葉脈部分は舌触りを悪くしますので、
なるべく枝につけたまま葉の部分だけそぎ落します。
乾燥した青じその葉の部分を手でそぎ落とします。
この時に、枝と葉をつないでいる太い葉脈部分は舌触りを悪くしますので、
なるべく枝につけたまま葉の部分だけそぎ落します。
 そぎ落とした青じその葉は、ジップロックなどに入れて、
手でもみながら細かく砕きます。
そぎ落とした青じその葉は、ジップロックなどに入れて、
手でもみながら細かく砕きます。
 写真のように細かく砕ければOKです。
葉が乾燥しているので、簡単に砕けると思いますが、
もし砕けないで葉のままの状態の場合は完全に乾燥していないと思われますので、
空のフライパンなどで弱火で焦がさないようにゆっくり炒りながら完全に乾燥させてから砕いて下さい。
写真のように細かく砕ければOKです。
葉が乾燥しているので、簡単に砕けると思いますが、
もし砕けないで葉のままの状態の場合は完全に乾燥していないと思われますので、
空のフライパンなどで弱火で焦がさないようにゆっくり炒りながら完全に乾燥させてから砕いて下さい。
 完成した乾燥青じそは、蓋付きの瓶などに入れて保管します。
お菓子などに入っている乾燥材があればそれを一緒に入れておけば一冬は持つと思います。
とは言っても時間が経ったり、湿気がある場所に保管したりすると風味が落ちてきますので、
翌年の青じそ収穫までのつなぎとしてなるべく早く消費することをお勧めします。
完成した乾燥青じそは、蓋付きの瓶などに入れて保管します。
お菓子などに入っている乾燥材があればそれを一緒に入れておけば一冬は持つと思います。
とは言っても時間が経ったり、湿気がある場所に保管したりすると風味が落ちてきますので、
翌年の青じそ収穫までのつなぎとしてなるべく早く消費することをお勧めします。
![]()
関連記事
青じそ(大葉)の育て方
青じそ(大葉)を苗から育てる
青じそ(大葉)をタネから育てる
青じそ(大葉)を地植えで育てる
青じそ(大葉)を挿し芽(挿し木)で増やす
青じそ(大葉)の苗のほぐし方
乾燥青じその作り方